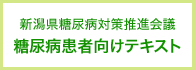診療内容・特色
※当院は日本内科学会認定教育関連病院・日本糖尿病学会認定教育施設・日本内分泌学会認定教育施設・日本動脈硬化学会認定専門医認定教育施設です。
内分泌・糖尿病内科では、糖尿病、ならびに甲状腺・副腎・下垂体・副甲状腺などの内分泌代謝疾患の診療を幅広く行っています。
糖尿病センターとして、患者さまによりよい治療を提供し、患者さま自身により適切な療養をしていただくために、医療スタッフが一体となったチーム医療を行っています。また、院内の様々な専門科と連携し、糖尿病の合併症の早期発見のための各種検査・合併症治療、および内分泌代謝疾患の診断・治療を、新潟医療センター全体として適切に行えるようになっています。
当科では、他の医療機関との地域医療連携にも積極的に取り組んでいます。病状の安定している患者さまを中心に、特に、普段はお近くの診療所に通院したい、待ち時間や予約の心配がないほうがいい、というご希望のある患者さまについては、お近くの開業医の先生にご紹介し、そちらを「かかりつけ医」にして通院していただきます。逆に、万一病状が悪化・急変した時にはご紹介していただき、スムーズに受け入れ出来るよう心がけています。また、高度な医療が必要な場合は、新潟大学医歯学総合病院などと連携しています。このような医療機関同士の協力体制で、患者さまにとって便利で安心できる診療を目指しています。
※患者さまにとって適切・安全な医療を行うために、他の医療機関に糖尿病や内分泌疾患(ホルモンの病気)で通院していた方は、紹介状をお持ちいただくようにしております。また、お薬手帳や糖尿病手帳は必ず持参してください。
糖尿病患者向けテキスト
2020年3月改訂
患者さま・ご家族・一般の方向けの無料テキスト
「知っておきたい『糖尿病』~やさしく学ぶための第一歩~」
どなたでも自由にダウンロードしてご利用いただけます。
糖尿病について
2型糖尿病は代表的な生活習慣病で、患者数が急増しています。糖尿病の合併症は、血糖値があまり高くない境界型=予備軍の時から始まっているのですが、糖尿病の症状自体は重症になってからはじめて出てくるため、病気を自覚していない場合が少なくありません。健康診断などで注意されても無視されがちで、気がついた時には合併症が相当に進んでいる人も少なくありません。毎年の健康診断を必ず受け、血糖値や尿糖を注意されたらきちんと医療機関を受診し、糖尿病、あるいは境界型と診断されたら、治療と定期的な受診を怠らず、血糖のコントロールができているか定期的にチェックすることが大切です。
このような理由から、新潟医療センターでは、皆さんの病気の早期発見・早期治療にお役に立てるように、健診センター業務にも力を入れています。詳細は健診センターのページをご覧ください。
さて、糖尿病の診察の目標は「糖尿病でも健やかに」です。合併症の発生予防や悪化予防を重視して、失明(中途失明の原因の第一位が糖尿病)・腎不全(人工透析の原因の第一位が糖尿病)・神経障害・心筋こうそく・脳こうそく・足の壊疽(えそ)などに至る可能性を極力抑えるため、食事療法や運動療法などの生活習慣指導や、合併症早期発見のための各種検査を行います。糖尿病になった原因は一人一人違いますから、食事療法や運動療法という自分の生活習慣に目を向けないと、コントロールは良くなりませんし、合併症も進行する可能性が高まります。
その他に、薬物療法として、1型糖尿病に対しては、人間の生理的なインスリン分泌を真似た「強化インスリン療法」を行い、厳密な血糖管理を行っています。2型糖尿病については、近年様々な作用の新しい薬が次々に登場していますし、早期に適切なインスリン治療を積極的に行うと、自前のインスリン分泌が回復し、弱い飲み薬や食事療法だけに戻すことができることも多い、ということも最近では有名になってきていますので、それらの治療も必要に応じて積極的に取り入れ、生涯にわたる良好なコントロールを目指します。また心筋こうそくなどの動脈硬化による疾患の発生・進行を極力予防するために、血圧やコレステロール・中性脂肪などの脂質などについても目をむけて、きちんと治療・コントロールしていきます。
新潟医療センター内分泌・糖尿病内科の糖尿病センターの特色は、患者さまにより適切な療養をしていただくために、医療スタッフ・病院全体が一体となった「チーム医療」を行っていることです。
外来では、まず、採血・採尿後、看護師による問診と血圧・体重測定を行い、検査部よりオンラインで送られてくる検査結果を待って、医師の診察となります。初回の受診の際には、食事療法などの適切な生活習慣の習得・合併症チェックなどに必要な、指導・検査の計画が立てられます。これに患者さま自身が協力して頂けないと、その後の診療はうまくいきません。
糖尿病治療の主役は、患者さまとそのご家族です。皆さんに糖尿病の治療・療養に必要な知識を身につけていただくことが、治療の大前提となります。その中心となる栄養指導については、治療にとって最も大切なことですので、初回は食事を作るご家族と一緒に時間をかけて念入りに行います。その後の通院中も、必要に応じて、待ち時間を利用した短時間の外来栄養指導によって、復習をこまめに行うことにより、効果が上がります(栄養科のページをご覧ください)。その他、治療に必要な知識を習得していただくために、毎月2回の糖尿病教室が行われています(このページの後ろのほうをご覧ください)。
血糖コントロール・教育のための入院は、専門スタッフによって、患者さま個々のペースに合わせた専門的かつ適切な治療・療養指導が集中的に行われます。実際の食事を食べてみることも、患者さまのその後の療養に役立ちます。
※当院ではアルコールなどの専門医師がおりません。アルコールなどに絡む問題行動がある場合、当科だけでは適切な治療ができませんので、専門機関への受診も併せて必要になります。
医療スタッフの間では、糖尿病チームミーティングが定期的に開かれ、医師・看護師・栄養士・薬剤師・理学療法士・検査技師・歯科衛生士・事務職員などが参加し、新潟医療センター全体としてより良い糖尿病診療を患者さまに提供できるよう、努力を続けています。医療スタッフは日本糖尿病療養指導士・新潟県地域糖尿病療養指導士制度にも積極的に参加し、療養指導士認定試験に合格し、幅広い知識を活用した丁寧な指導によって患者さまがより良い療養ができるよう、日々頑張っています。また足の病変について専門的な知識を有するスタッフもおり、皆さんの力強い味方になってくれます。
更に、眼科・腎臓内科・循環器内科・脳神経内科・脳神経外科・整形外科・皮膚科・歯科などを中心とする院内の各専門科と連携し、糖尿病の合併症の早期発見のための各種検査・合併症の治療を、新潟医療センター全体として適切に行えるようなっています。
※当科はインスリンポンプには対応しておりません。ご了承ください。
内分泌代謝疾患について
甲状腺疾患では、バセドウ病や橋本病(慢性甲状腺炎)などの甲状腺ホルモン過剰(甲状腺機能亢進症)・欠乏(甲状腺機能低下症)についての診断、薬物療法に対応しています。アイソトープ治療・手術療法などが必要な場合は、適切な他の医療機関にご紹介し、治療がきちんと行えるよう手配しています。
副腎疾患(クッシング症候群、原発性アルドステロン病、褐色細胞腫、副腎皮質機能低下症など)、視床下部・下垂体疾患(先端巨大症、クッシング病、プロラクチノーマ、下垂体機能低下症、尿崩症など)、副甲状腺疾患などについては、専門医の診察のもと、必要な検査を行って診断し、泌尿器科・脳神経外科・外科・産婦人科・耳鼻咽喉科などの院内の各種専門科と連携し、当院または他の医療機関にて治療しています。
※当科は男性更年期、神経性食思不振症、環境ホルモン関連には対応しておりません。ご了承ください。
糖尿病教室のご案内
※感染症の流行状況によって休止となる場合があります。
| 開催日 | 第1・第3火曜日 |
|---|---|
| 申し込み先 | 内分泌・糖尿病内科(糖尿病センター)外来 |
| 目的 | 糖尿病治療の主役である患者さまとその家族に、 治療・療養に必要な知識を身につけていただくことを目的としています。 |
| 対象 | 糖尿病患者さまご本人とその家族、又はお世話をする人 (食事を作る人と一緒に参加してください) |
| 場所 | 栄養相談室(病院1階) |
糖尿病教室日程表
| 時間 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|
| 13:15 | 検査でわかるコントロール状態と合併症 糖尿病と検査 |
臨床検査技師 |
| 14:00 | おいしく楽しい食事のために! 糖尿病の食事療法 |
管理栄養士 |
| 糖尿病ってどんな病気? 糖尿病の概要 |
医師 | |
| 14:20 | (休憩) | |
| 14:25 | 食べる楽しみいつまでも 糖尿病と歯の関係 |
歯科衛生士 |
| 14:40 | お薬と仲よくなろう!! 糖尿病と薬剤 |
薬剤師 |
| 15:05 | (休憩) | |
| 15:10 | 体を動かす習慣をつけよう! 糖尿病と運動 |
理学療法士 |
| 15:30 | 知らないと怖い 合併症とその治療 |
医師 |
| 15:45 16:00 |
自分でできる5つのはかり 糖尿病と日常生活 |
看護師 |
- 外来の患者さまは、当日受付においでください。
- 糖尿病という病気の説明・治療方法についてまとめたテキスト「糖尿病とともに」を当院売店で購入してください。(400円)
- 筆記用具を用意してください。
- 自己血糖測定・インスリン自己注射をされている方は、道具をご持参ください。
- 万歩計を使用されている方は持参してください。
内分泌・糖尿病内科にはじめて受診する患者さまへ
予めご了解をお願い申し上げます。
当科通院の場合は、平日午前中の医師指定の予約日時に来院していただき、原則として当日の診察前採血や検尿などの結果を待っての診察となります。(なお、現在、内分泌・糖尿病外来はどの医療機関も混雑しています。当科も予約人数が定数枠を超えていることがしばしばあり、長時間お持たせすることがあります。申し訳ございません)。予約受診の間隔は病状にあわせて医師が決定させていただきます。
定期的に予約日時通りに来院できない方・診察前検査のできない方などは、治療に支障を来し危険ですので、お近くの医療機関へ通院していただくことになります。
スタッフ紹介
部長
五十嵐 智雄
| 略歴 | 平成8年 新潟大学医学部卒業 医学博士 労働衛生コンサルト(労働衛生工学・保健衛生) 臨床心理士、公認心理師 ※1 衛生工学衛生管理者 作業環境測定士(第一種第二号) |
|---|---|
| 認定資格等 |
日本内科学会認定総合内科専門医・指導医 日本内分泌学会認定内分泌代謝科(内科)専門医・指導医・評議員 日本糖尿病学会認定糖尿病専門医・指導医・学術評議員 内分泌代謝・糖尿病内科領域専門研修指導医 日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医・指導医 日本専門医機構認定総合診療領域特任指導医 日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医・評議員、産業医・実地医家部会委員 日本総合健診医学会・日本人間ドック学会認定人間ドック健診専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 日本医師会認定産業医 ICD制度協議会認定インフェクションコントロールドクター 認知症サポート医 ※2 日本スポーツ協会公認スポーツドクター |
| 所属学会 |
日本内科学会 日本内分泌学会 日本糖尿病学会 日本甲状腺学会 日本動脈硬化学会 日本人間ドック学会 日本総合健診医学会 日本プライマリ・ケア連合学会 日本環境感染学会 日本リハビリテーション医学会 日本心身医学学会 日本臨床心理士会 日本産業衛生学会 日本労働安全衛生コンサルタント会 |
※1 カウンセリングや、こころや精神の疾患の診療は行っておりません。
※2 認知症の診断や診療をご希望の場合は、脳神経内科にご相談下さい。
羽賀 雅記
部長(循環器内科との兼務)
冨井 亜佐子
(新潟大学医歯学総合病院 内分泌・代謝内科医師)
大学医
- ※ 当院は臨床研修病院であり、臨床研修医が、指導医の指導のもとで診療を担当させていただく場合があります。ご了承ください。
- ※ 学会出張・救急対応などのため代診・休診・受付時間の短縮などの変更が生じる場合があります。ホームページで随時ご案内いたしますが、やむを得ず予定外の休診・代診等になる場合もありますので、事前にご確認のうえご来院ください。
外来診療時間
受付時間は「外来診療担当医表」をご確認ください。